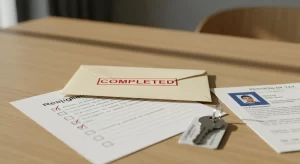「会社を辞めたいけど、退職代行の費用はどれくらいかかるんだろう…」「追加料金を請求されたらどうしよう」と、金銭的な不安から一歩踏み出せずにいませんか。退職代行サービスの料金は、運営元によって大きく異なります。
この記事では、退職代行の費用相場から追加料金が発生するケース、そして損をしないための選び方のコツまで詳しく解説します。この記事を読めば、あなたに合った費用対効果の高いサービスを見つけ、安心して退職手続きを進めることができます。
退職代行の費用相場はどれくらいかかるのか?

退職代行サービスの費用相場は、運営元の形態によって大きく異なり、一般的には2万円台から10万円以上と幅があります。最も安価なのは民間企業運営ですが、サービス範囲に制限があるため注意が必要です。
一方、労働組合や弁護士事務所が運営するサービスは、会社との交渉が可能で安心感が高いですが、その分費用も高くなる傾向にあります。自分の状況や求めるサービス内容に合わせて、最適な運営元を選ぶことが重要になります。
運営形態別で見る退職代行の料金相場を比較
退職代行サービスを選ぶうえで、運営元が「民間企業」「労働組合」「弁護士事務所」のどれに該当するかは非常に重要です。なぜなら、運営元によって対応できる業務範囲と料金が大きく異なるからです。
例えば、未払いの残業代や有給休暇の消化について会社と交渉したい場合、交渉権を持たない民間企業では対応できません。以下の表でそれぞれの特徴を比較し、自分の希望に合ったサービスを見つけましょう。
| 運営形態 | 費用相場 | サービス内容(交渉の可否) |
|---|---|---|
| 労働組合 | 25,000円~30,000円 | 団体交渉権があり、有給消化や未払い賃金の交渉が可能 |
| 弁護士事務所 | 50,000円~ | 訴訟対応など法律に関するあらゆる交渉・請求が可能 |
| 民間企業 | 20,000円~30,000円 | 交渉権はなく、退職意思の伝達のみ |
労働組合が運営する場合の費用とサービス内容
労働組合が運営する退職代行の費用相場は、25,000円から30,000円程度で、コストパフォーマンスに優れています。労働組合は労働者の権利として「団体交渉権」を持っているため、退職日の調整はもちろん、有給休暇の消化や未払い残業代の請求といった交渉が可能です。
弁護士に依頼するよりも費用を抑えつつ、会社との交渉を任せたいという方におすすめの選択肢です。退職時に会社と交渉したいことがある場合は、労働組合が運営するサービスを検討しましょう。
弁護士事務所に依頼する場合の費用とメリット
弁護士事務所が運営する退職代行の費用は、50,000円以上が相場で、他の運営形態に比べて高額になる傾向があります。しかし、その分サービス内容は最も充実しており、法律の専門家である弁護士が代理人としてすべての手続きを行います。
未払い給与の請求や退職金の交渉はもちろん、パワハラに対する慰謝料請求や損害賠償請求といった訴訟に発展する可能性がある複雑なケースにも対応可能です。法的なトラブルを抱えている方にとって、最も安心感の高い選択肢と言えるでしょう。
民間企業が運営する場合の費用と注意すべき点
民間企業が運営する退職代行サービスは、費用相場が20,000円から30,000円程度と比較的安価なのが特徴です。しかし、弁護士や労働組合と異なり、法律で認められた交渉権を持っていません。
そのため、業務内容はあくまで「退職の意思を本人に代わって伝える」ことに限定されます。有給消化の交渉などを行うと非弁行為という違法行為にあたるリスクがあるため注意が必要です。トラブルなく、ただ退職の連絡だけを代行してほしい場合に適しています。
退職代行の追加料金は?料金の内訳と発生事例

退職代行サービスの多くは「追加料金一切なし」を謳っていますが、依頼内容や状況によっては追加費用が発生するケースも存在します。契約前に追加料金の有無や、基本料金に含まれるサービス範囲をしっかり確認することがトラブル回避の鍵です。
万が一の出費で後悔しないためにも、料金体系が明確な業者を選ぶことが重要です。ここでは、基本料金の内訳や追加料金が発生する具体的な事例について詳しく見ていきましょう。
基本料金に含まれる一般的なサービス内容を確認
退職代行の基本料金には、一般的に退職を完了させるまでの一連のサポートが含まれています。具体的には、会社への退職意思の伝達、退職日の調整、退職届の提出代行、貸与品の返却手続きの案内などです。
また、多くの業者では相談回数に制限がなく、LINEやメールで24時間いつでも相談できる体制を整えています。不安なことがあればいつでも担当者に連絡できるため、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。
要注意!こんなケースでは追加料金がかかることも
一律料金を掲げる業者が多いものの、特定の状況下では追加料金が必要になることがあります。例えば、会社から損害賠償請求をされるなど、法的な紛争に発展し訴訟対応が必要になった場合です。この場合、弁護士への依頼が別途必要になります。
また、深夜や早朝の緊急対応を依頼する場合や、退職金や未払い賃金の請求で成功報酬が発生するプランもあります。契約前に、どのような場合に費用が発生するのか、利用規約を隅々まで確認しておきましょう。
各種支払い方法と分割払いの利用可否について
退職代行サービスの支払い方法は、クレジットカード決済と銀行振込が一般的です。すぐにまとまったお金を用意するのが難しいという方のために、後払いや分割払いに対応している業者も増えています。
特にクレジットカードを持っていれば、カード会社の分割払い機能を利用して支払いの負担を軽減できます。金銭的な不安がある場合は、公式サイトで利用可能な支払い方法を事前にチェックしたり、無料相談で分割払いの可否を確認してみましょう。
費用で損しない退職代行サービスの選び方のコツ

退職代行サービスで損をしないためには、料金の安さだけで判断するのではなく、サービスの質や信頼性を総合的に見極めることが不可欠です。安易な選択は、退職失敗や思わぬトラブルにつながる危険性があります。
ここでは、安心して依頼できる退職代行サービスを見つけるための4つの重要なコツを紹介します。これらのポイントを押さえることで、費用面でもサービス面でも満足のいく退職が実現できるでしょう。
料金の安さだけで選ぶことの危険性と失敗例
相場よりも極端に安い料金を提示している業者には注意が必要です。安さの裏には、サポート体制が不十分であったり、違法な非弁行為を行うリスクが隠れていたりする可能性があります。
失敗例としては、「会社から連絡が来ても対応してくれなかった」「有給消化の交渉をしてもらえず、結局自分で連絡するはめになった」といったケースが挙げられます。確実かつ円満に退職するためには、料金だけでなくサービス内容や実績を重視することが大切です。
運営元が労働組合か弁護士法人であるかを確認
退職代行で最も重要なチェックポイントは、運営元がどこかという点です。適法に会社との交渉を行えるのは、団体交渉権を持つ「労働組合」か、代理人として活動できる「弁護士法人」のみです。
民間企業が運営するサービスでも、弁護士が監修している場合がありますが、交渉自体はできません。有給消化や未払い給与の交渉を希望する場合は、必ず運営元が労働組合か弁護士法人であることを公式サイトで確認しましょう。
料金体系の明確さと返金保証の有無は重要
信頼できる業者は、料金体系が非常に明確です。公式サイトに基本料金で対応可能なサービス範囲や、追加料金が発生するケースが具体的に記載されています。見積もりを依頼した際に、不明瞭な点がないか必ずチェックしましょう。
また、「退職できなかった場合は全額返金保証」といった制度の有無も大きな判断材料になります。返金保証がある業者は、それだけサービスに自信を持っている証拠であり、利用者も万が一のリスクを心配することなく安心して依頼できます。
過去の実績や利用者からの口コミ評判を参考に
公式サイトに掲載されている「退職成功率〇%」といった実績は重要な指標ですが、それだけを鵜呑みにするのは危険です。よりリアルな情報を得るためには、X(旧Twitter)などのSNSや口コミサイトで、実際に利用した人の評判を確認しましょう。
良い口コミだけでなく、悪い口コミの内容にも目を通すことで、そのサービスのメリット・デメリットを多角的に把握できます。担当者の対応の丁寧さや連絡の速さなど、具体的な評価を参考にすることで、自分に合った業者を選びやすくなります。
退職代行はどれくらいの日数で辞められるのか?

「明日からもう会社に行きたくない…」という切実な悩みに対し、多くの退職代行サービスは「即日退職」で応えてくれます。これは依頼した翌日から出社が不要になる仕組みで、法律的にも問題ありません。
なぜそのようなことが可能なのか、その仕組みを理解することで、より安心してサービスを利用できます。ここでは、即日退職が実現する具体的な理由と、依頼から退職完了までの流れを分かりやすく解説します。
依頼の翌日から出社不要になる即日退職の仕組み
即日退職が可能になる背景には、民法の規定があります。民法第627条では、雇用期間の定めがない場合、退職の意思表示から2週間が経過することで雇用契約が終了すると定められています。
退職代行業者は、まず会社に退職の意思を伝えます。そして、法律上退職が成立するまでの2週間は、残っている有給休暇を消化するか、それがなければ欠勤扱いとすることで、実質的に出社しない状況を作り出すのです。
有給休暇の消化や欠勤扱いで実質的に即日退職
依頼者が退職の意思を固めたら、退職代行業者が本人に代わって会社に連絡し、有給休暇の消化を申請します。労働者にとって有給休暇の取得は権利であり、会社側は原則としてこれを拒否できません。
もし有給休暇が残っていなかったり、足りなかったりする場合でも心配は不要です。その場合は、退職日までの期間を「欠勤扱い」にしてもらうよう会社と調整します。これにより、依頼者は一度も出社することなく退職日を迎えることができます。
依頼から退職完了までの具体的な流れを解説
退職代行を依頼してから退職が完了するまでの流れは非常にシンプルです。多くの業者では、LINEやメールでのやり取りだけで完結し、直接会ったり電話したりする必要もありません。具体的な手順は以下の通りです。
- ステップ1:相談・申し込み
公式サイトのフォームやLINEから、無料相談と申し込みを行います。24時間対応している業者がほとんどです。 - ステップ2:支払い
サービス内容と料金に納得したら、クレジットカードや銀行振込で料金を支払います。 - ステップ3:担当者との打ち合わせ
担当者と今後の流れや会社に伝えてほしい希望(退職理由など)を具体的に打ち合わせします。 - ステップ4:退職代行の実行
指定した日時に、業者が会社へ連絡し、退職の意思を伝えます。 - ステップ5:退職完了
会社とのやり取りが完了し、離職票などの必要書類が届けば、すべての手続きが完了です。
まとめ:退職代行の費用で損しないための選び方

退職代行サービスの費用は2万円台から10万円以上と幅広く、運営元によってサービス内容が大きく異なります。費用で損をせず、確実に退職するためには、安さだけで選ぶのは非常に危険です。
重要なのは、会社との交渉が必要な場合は「労働組合」か「弁護士法人」が運営するサービスを選ぶこと、料金体系が明確で「追加料金」の心配がないこと、そして「返金保証」があるかどうかを確認することです。この記事を参考に、あなたの状況に最適なサービスを見つけて、円満な退職を実現してください。
退職代行の費用や期間に関するよくある質問

依頼したその日に辞めることは本当に可能ですか?
はい、可能です。多くの退職代行サービスでは、依頼を受けた当日に会社へ連絡し、翌日から出社不要となる「即日退職」に対応しています。法的には退職の申し入れから2週間が必要ですが、その期間は有給消化や欠勤扱いとすることで対応します。
そのため、依頼者は会社の上司や同僚と顔を合わせることなく、実質的にその日から退職に向けた手続きを進めることができます。心身ともに限界な状況でも、すぐに職場から離れられる安心の制度です。
明日からもう会社に行かなくても大丈夫ですか?
はい、問題ありません。退職代行サービスに依頼した後は、業者が必要な連絡をすべて代行してくれます。あなた自身が上司や人事に電話をしたり、出社したりする必要は一切ありません。
退職届の提出や貸与品の返却なども、基本的には郵送でのやり取りとなります。業者の指示に従って手続きを進めれば、スムーズに退職が完了するのでご安心ください。
有給休暇がなくても即日退職できるのでしょうか?
はい、有給休暇が残っていなくても即日退職は可能です。退職の意思を伝えてから退職日が成立するまでの期間を「欠勤扱い」とすることで対応するのが一般的です。
欠勤扱いになることで給与や評価に影響が出る可能性はありますが、すでに退職を決意している状況では大きなデメリットにはなりません。有給の有無を気にせず、まずは退職代行サービスに相談してみることをおすすめします。
退職代行の利用で後悔する落とし穴はありますか?
最も多い後悔のパターンは、料金の安さだけでサービスを選んでしまうことです。交渉権のない民間企業に依頼してしまい、有給消化の交渉をしてもらえずトラブルになったり、サポートが不十分で不安な思いをしたりするケースがあります。
このような失敗を避けるためにも、運営元が労働組合か弁護士法人であるか、料金体系は明確か、口コミの評判は良いかなどを総合的に判断することが重要です。
退職代行を使って即日退職することは違法ですか?
いいえ、退職代行サービスの利用や即日退職は全く違法ではありません。労働者には「退職の自由」が法律で保障されており、その意思を伝える方法に制限はありません。
弁護士や労働組合が運営する適法なサービスを選べば、法律に則って手続きを進めてくれるため、会社から不当な損害賠償を請求されるといったトラブルの心配もありません。安心して依頼してください。